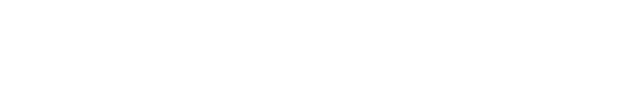大腸がんとは?
症状・原因・検診・検査・ステージ・治療について解説
ある程度の年齢になるとがんのことが気になりますね。
40歳以上になると大腸がんのリスクが高くなります。
大腸がんはどのような病気なのでしょうか。
本記事では、大腸がんの定義、疫学、症状、病態・原因、検診、検査、病期、治療、余命について解説します。
これを読めば大腸がんの概略が分かります。
大腸がんの検査や治療をする際に参考にしてください。
大腸がんとは
大腸の粘膜にできるがんです。
日本人ではS状結腸や直腸にできやすいのが特徴です。
良性のポリープががん化する場合と、正常な粘膜からがんが発生する場合があります。
がんは進行すると大腸の壁に深く侵入していき、大腸の壁の外にまで広がります。
がん細胞が腹腔内に散らばるのが腹膜播種(ふくまくはしゅ)です。
リンパ管や血管を介して肝臓や肺などに転移することがあります。(注1
大腸がんの疫学
大腸がんは日本人によくみられる病気です。
2019年に日本全国で155,625人の大腸がん患者がみられました。
また2020年の大腸がんによる死亡数は51,788人でした。(注2
日本で増えているがんといっても過言ではないでしょう。
大腸がんの症状
症状は病期により異なります。
初期症状
初期症状はほとんどありません。
たいていは大腸がん検診(便潜血検査)などでみつかります。(注1
進行期の症状
進行すると以下のような症状がみられます。
ただし全ての症状がそろうわけではありません。
- 便に血が混じる(血便・下血)
- 便の表面に血が付く
- 出血が続くと貧血となる
- 腸が狭くなることで、便が細くなる、便秘、下痢、残便感、おなかの張りがみられる
- 腸閉塞になると腹痛、嘔吐をおこす
- 体重減少(注1
大腸がんの病態・原因
大腸がんでみられる構造や機能の変化(病態)と、それを引き起こす原因について解説します。
病態
がんとはがん細胞の塊です。
そしてがん細胞は遺伝子変異で死ななくなった細胞です。
人の体には約60兆個の細胞があり、毎日1%が死滅し、細胞分裂で細胞を補っています。
細胞分裂の設計図は遺伝子で、毎日遺伝子を数千億回コピーします。
コピーミスで細胞が突然変異すると、細胞が死ななくなり、とめどなく分裂するようになったものががん細胞です。
正常な人でもがん細胞は毎日発生しますが、免疫細胞ががん細胞を退治するため、がんになりません。
ところが時にがん細胞が生き残り、10~20年かけて大きくなってがんができます。(注3
原因
がんは老化の一種と考えられます。
つまり長生きするとがん細胞が増えるとともに、免疫細胞の機能が衰えます。
この結果、がんができやすくなるわけです。(注3
喫煙・飲酒・肥満・糖尿病は大腸がんの発生リスク因子です。
また加工肉なども発生リスク因子との報告もあります。
さらに家族で大腸がんの人がいるとかかりやすいのが特徴です。(注1
大腸がん検診
大腸がん検診は、大腸がんを早期に発見し、適切な治療をおこない、死亡数を減らすのが目的です。
年に1回、40歳以上で症状のない健康な人を対象にして行われます。(自治体による)
大腸がん検診の内容は、主に便潜血反応検査です。
便潜血反応は、2日分の便を取って血が便に混じっていないかを調べます。
要精密検査になった場合は大腸内視鏡(大腸カメラ)などで精密検査が必要です。(注1
大腸がんの検査
大腸がんの精密検査には、大腸内視鏡検査・注腸造影検査・CT・MRI検査・PET検査・腫瘍マーカーなどが含まれます。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
肛門から内視鏡を挿入して大腸を調べる検査です。
検査の前日から検査食と下剤を服用し、検査当日腸管洗浄液を服用して、大腸の中をきれいにしてから検査します。
大腸の粘膜の変化を観察し、必要時病変を生検し、がんの有無を調べます。
色素を散布して病変を強調することもあります。(注1
大腸ポリープがみられた場合は、その場で切除する場合もあります。
注腸造影検査
バリウムと空気を肛門から注入し、大腸がレントゲンに映るようにして検査します。
大腸内視鏡検査と同じように大腸の中をきれいにしてから調べます。
病変の位置、大きさ、範囲、形、大腸の広がりなどをみます。(注1
CT・MRI検査
CT はX線、MRIは磁気を使って体の中を調べる検査です。
大腸がんが広がり、周囲の臓器へ浸潤していないか、肝臓や肺などの臓器へ転移していないかを調べます。(注1
PET検査
放射性ブドウ糖液を注射して、がん細胞への取り込み状況を撮影し、がんの全身への転移・再発の有無を調べる検査です。
CT・MRIでは分からない病巣がみつかります。(注1
腫瘍マーカー
腫瘍マーカーとは、がん細胞やがん細胞に反応した細胞が生み出すタンパク質などのことです。
大腸がんではCEA・CA19-9などを調べます。
手術後の再発の有無、薬物療法の効果判定などに利用されます。
ただし腫瘍マーカーだけではがんの有無は分からないため、他の検査結果と合わせて診断します。(注1
大腸がんの病期
検査の結果から、大腸がんの進み具合、つまり病期を判定します。
病期には深達度とステージが含まれます。
深達度
大腸がんの深さを表す指標です。
大腸の壁は、浅いところから深いほうへ向かって、粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層または外膜、漿膜の構造をもちます。
大腸がんが、どの構造まで進んでいるかで分類します。
- Tis:がんが粘膜面にとどまる(ごく浅い)
- T1:がんが粘膜下層にとどまる(浅い)
- T2:がんが固有筋層にとどまる(中間)
- T3:がんが固有筋層と漿膜下層または外膜の間にある(深い)
- T4a:がんが大腸の外壁から顔を出している(かなり深い)
- T4b:大腸周囲の臓器へ浸潤
数字が大きいほどがんは広がっており、Tis~T1は早期がん、T2~T4は進行がんと呼ばれます。(注1
ステージ
転移の有無も含めて、以下のような病期分類(ステージ分類)がよく用いられます。
- 0期:がんが粘膜面にとどまる
- Ⅰ期:がんが固有筋層にとどまる
- Ⅱ期:がんが固有筋層の外まで浸潤
- Ⅲ期:リンパ節転移がある
- Ⅳ期:血行性転移または腹膜播種がある
数字が大きいほどがんは広がっています。(注1
大腸がんの治療
大腸がんの病期に合わせて、治療法を検討します。
治療法には、内視鏡治療・手術治療・全身化学療法・放射線療法が含まれます。
内視鏡治療
内視鏡を使って大腸がんを切除する方法です。
大腸がんが粘膜内にとどまる、または粘膜下層へ軽度浸潤している程度で、リンパ節転移の可能性がほとんど全くない場合に実施が検討されます。
医療用のスネア・専用のナイフで病変部位を切除、回収します。
開腹手術でなくても大腸がんを治療できるのがメリットです。
ただし高度な技術を要し、消化器内科専門医がいる医療機関でのみ治療可能です。
治療後、内視鏡検査・CT検査などでフォローしながら再発・転移の有無をチェックします。(注4
手術治療
内視鏡治療ができない場合(進行大腸がん)は手術治療が検討されます。
がんおよびがんが広がっている可能性のある腸管・リンパ節を切除します。
がんから約10㎝離れた部位で腸管を切除するのが原則です。
がんがある場所によって切除する腸管が変わります。
また後に残った腸管をつなぎ合わせ、つなぎ合わせることができない場合は人工肛門を増設します。
さらにがんが広がっている周囲の臓器の一部を切除することがあります。
とりわけ直腸がんは、周りに膀胱・前立腺・子宮・卵巣・肛門があり、切除する範囲を決めるのが難しいのが特徴です。
直腸がんの手術の場合、肛門括約筋、排尿機能や性機能を調節する自律神経をできるだけ残すのが理想ですが、がんが浸潤していれば切除せざるをえません。
その場合、排便機能・排尿機能・性機能に支障を来します。(注1
腹腔鏡下手術
おなかに小さな穴を開けて、二酸化炭素でおなかをふくらませ、腹腔鏡などを挿入して、おなかの中で手術する方法です。
開腹手術と比べると、難しく、時間がかかりますが、手術後の回復が早いのがメリットです。
がんの進行度、肥満の程度、術者の技量などで適用が決定されます。(注1
再発性大腸がんの治療方針
手術後に大腸がんが再発した場合、切除可能であれば手術治療が選択されます。
切除不可能で全身状態が良い場合は、全身化学療法、放射線療法の適用です。
切除不可能で全身状態が良くない場合は、対症療法が行われます。(注3
血行性転移の治療方針
血行性に転移している場合でも、転移した病巣が切除可能であれば、手術治療を行います。
切除不可能で全身状態が良い場合は、全身化学療法、放射線療法の適用です。
切除不可能で全身状態が良くない場合は緩和医療が行われます。(注3
全身化学療法
抗がん薬などの薬物による治療法です。
補助化学療法
再発リスクが高いがんに対して手術後の再発抑制のために行われます。
患者さんの年齢、持病、副作用に対する反応、治療意欲、治療コストなどから治療方針を決めます。
術後8カ月までに開始し、6カ月続けることが原則です。(注3
切除不能進行・再発大腸癌に対する薬物療法
延命と症状コントロールが目的です。
切除不能な大腸がんで、抗がん薬による化学療法を行わなかった場合は平均余命約8カ月。
それに対して、抗がん薬による薬物療法を行った場合は平均余命約30カ月と報告されています。
しかし完全な治癒を望むのは難しい現状です。
ただし転移巣が縮小して手術で切除できるようになることがあります。(注3
放射線療法
手術療法を補助するため、切除不能な進行がんの症状を緩和するために放射線療法が行われます。
補助放射線療法
直腸がんの術前照射で腫瘍を縮小させ、切除範囲を縮小して、肛門括約筋を残す手術を可能にする目的で放射線量が用いられます。
ただし生存率の改善効果は不明であり、術後の合併症が増えるリスクを伴うのがデメリットです。
術後照射で局所のがん再発を予防する場合があります。
ただし生存率は改善せず、肛門の感覚異常、頻便、排便困難の副作用を起こすことがあるのがデメリットです。(注3
緩和的放射線療法
切除不能の進行がんの症状を緩和し、延命させる目的で行われます。
たとえば以下のような事例です。
- 骨盤内腫瘍による疼痛、出血、便通異常の緩和
- 骨転移による疼痛の軽減、病的骨折の予防、脊髄麻痺の予防
- 脳転移による頭蓋内圧亢進症状の緩和・延命(注3
大腸がんの余命(予後)
大腸がんにかかった場合、あとどのくらい生きられるかを推定するために、5年生存率が用いられます。
5年生存率とは、がんにかかった人の集団のうち、何パーセントが5年後に生きているかという統計です。
診断された年は2015年の大腸がん患者の5年生存率を示します。
ただしがんによる死亡だけでなく、すべての死因を含めた生存率です。
- ステージⅠ:83.2%
- ステージⅡ:76.2%
- ステージⅢ:69.0%
- ステージⅣ:17.2%
ステージが進むほど生存率が低くなります。(注4
まとめ
大腸がんは大腸の粘膜にできるがんです。
初期の症状はほとんど全くありません。
大腸がん検診で精査をすすめられ、大腸内視鏡検査・CT検査などで診断されます。
検査結果から病期を判定し、治療法を検討します。
治療法には、内視鏡治療・手術治療・全身薬物療法・放射線療法が含まれます。
当院では鎮静剤を使用した痛みのない大腸カメラ検査をおこなっております。