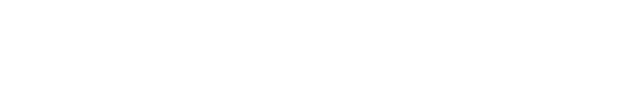肝臓がんとは?
原因・症状・検査・治療について解説
検診などで肝臓がんを疑われることがあります。
それでは肝臓がんとはどのような病気なのでしょうか?
本記事では、肝臓がんの種類、原因、症状、診断、検査、治療、余命について解説します。
これを読めば、肝臓がんの概要が分かります。
肝臓がんの検査、治療をする際に役立ててみてください。
1.肝臓がんとは?
肝臓の細胞ががん化したものです。
肝臓から発生する原発性肝がんが主な肝臓がんです。
他の臓器のがんが転移した転移性肝がん、肝内胆管がん、小児の肝細胞芽腫(かんさいぼうがしゅ)なども含まれます。
原発性肝臓がんは50歳代から増加し、80~90歳代に最も多くみられます。(注1
2.肝臓がんの原因
がんは遺伝子の突然変異によってできたがん細胞の塊です。
肝臓の持続的な炎症により、繰り返し肝臓の細胞が破壊されると、肝臓がんが生じやすくなります。
たとえば以下のような場合です。
- B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの持続感染による慢性肝炎や肝硬変
- 肝炎ウイルス感染があって、慢性肝炎や肝硬変がほとんど全くない状態から肝臓がんになることもあります
- 自己免疫性肝炎から慢性肝炎になる
- アルコール性肝障害
- 肥満・糖尿病・脂質異常症で肝臓に脂肪がたまり、非アルコール性脂肪肝炎から肝硬変になる
また男性・高齢・喫煙もリスクファクターです。(注1
3.肝臓がんの症状
肝臓がんを起こす原因や病期によって症状は異なります。(注1
3-1.肝臓がんの初期症状
慢性肝炎や肝硬変がほとんど全くない状態から肝臓がんになった場合、ほとんど全く自覚症状がありません。
大抵は検診や他の病気で検査中にみつかります。(注1
3-2.肝臓がんの症状チェックリスト
慢性肝炎・肝硬変を経て肝臓がんになった場合は以下のような症状が現れます。(注1
3-2-1.慢性肝炎・肝硬変になるとみられる症状
- 食欲不振
- むくみ
- 倦怠感(けんたいかん)(注1
3-2-2.肝臓がんになるとみられる症状
- 腹部の圧迫感
- 腹部のしこり(注1
4.肝臓がんの診断・検査
既往歴、生活歴、検査結果などをもとに肝臓がんを診断します。
4-1.既往歴・生活歴等
B型慢性肝炎・C型慢性肝炎・肝硬変・糖尿病の有無・年齢・性別・BMI・飲酒量などのリスクファクターの有無を確認します。(注2
4-2.血液検査
一般的な血液検査のうちでAST・ALT・血小板に異常値を認めます。
これは肝臓がんに特異的な検査ではありませんが、スクリーニング検査として用いられます。(注2
4-3.腫瘍マーカー
肝臓がんが疑われる場合、もしくは人間ドックでは、AFP、AFPレクチン分画、PIVKA-Ⅱといった腫瘍マーカーを測定します。
高リスク群では6カ月ごと、とりわけリスクが高い群では3~4カ月ごとの検査が望まれます。(注2
4-4.腹部エコー
続いて腹部の超音波検査で肝腫瘍を検出します。
高リスク群では6カ月ごと、とりわけリスクが高い群では3~4カ月ごとの検査が望まれます。
腫瘍を見つけたらさらに他の検査を行います。(注2
4-5.CT・MRI
高度肥満、肝臓の萎縮がみられ、腹部エコーによって小さな肝臓がんを見つけにくい場合、dynamic CT・dynamic MRIが有用です。
この検査では、造影剤を速い速度で注入し、動脈が染まる相、静脈が染まる相にタイミングを合わせて撮影します。
動脈相で濃染像の出現、静脈(門脈)相で濃染像の消失が認められれば肝臓がんと診断されます。
Dynamic CTよりもdynamic MRIのほうが感度が高いのが特徴です。
この検査でも診断できない場合、Gd-EOB-DTPA 造影MRIが有用です。(注2
Gd-EOB-DTPAは肝臓に特異的に取り込まれる造影剤であり、肝動脈あるいは門脈にカテーテルを置き、そこから造影剤を注入して撮影します。(注3
4-6.FDG-PET
放射性ブドウ糖液を注射して、がん細胞への取り込み状況を撮影し、肝臓がんの転移の有無を調べる検査です。
4-7.胸部CT・骨シンチグラフィー
FDG-PETができないとき、胸部CT・骨シンチグラフィーで肝臓がんの転移の有無を調べます。
肺への転移はFDG-PETよりも胸部CTのほうが感度が高いです。
5.肝臓がんのステージ分類
肝臓がんの数、大きさ、脈管への広がり、リンパ節転移、遠隔転移の有無により、ステージ(病期)Ⅰ~Ⅳが決まります。
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|
|
3項目全て合致 | 2項目合致 | 1項目合致 | 全て合致せず |
| リンパ節・遠隔臓器に転移がない | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | ⅣA期 |
| リンパ節に転移はあるが、遠隔転移はない | ⅣA期 | |||
| 遠隔転移がある | ⅣB期 | |||
(注4
6.肝臓がんの治療
肝臓がんは病態に応じてさまざまな治療法があります。
6-1.治療法の選択
腫瘍の数、大きさ、脈管侵襲、肝外転移、肝予備能をもとに治療法が選択されます。
- 腫瘍数1~3個、腫瘍径3cm以内の場合:肝切除または焼灼(しょうしゃく)療法
- 腫瘍数1~3個、腫瘍径3cm以上の場合:肝切除または塞栓療法
- 腫瘍数4個以上の場合:塞栓療法、肝動注化学療法または薬物療法
- 肝外転移がなく脈管侵襲を伴う場合:肝切除または薬物療法
- 肝臓の機能が良好で肝外転移がある場合:薬物療法
- 肝臓の機能が不良の場合:肝移植または緩和ケア(注2
6-2.肝切除
手術により、がんと周囲の肝臓の一部を取り除く治療法です。
開腹手術が原則ですが、場合によっては腹腔鏡下手術が行われることもあります。(注4
6-3.焼灼療法
腹部エコーで腫瘍を確認しながら、腫瘍の内部に約1.5mm径の針(電極)を挿入して、ラジオ波で熱を発生させて病変を焼き切る治療です。
腹腔鏡下や開腹下で行うこともあります。(注5
6-4.塞栓療法
足の付け根、肘、手首の動脈からカテーテルを挿入し、肝臓がんの近くまで進めて治療する方法です。
6-4-1.肝動脈化学塞栓療法
肝臓がんに栄養を運んでいる肝動脈から抗がん薬を注入し、さらに肝動脈をつまらせる塞栓物質を注入して治療します。(注4
6-4-2.肝動脈塞栓療法
肝臓がんに栄養を運んでいる肝動脈をつまらせて、肝臓がんの増殖をおさせる治療法です。(注4
6-5.肝動注化学療法
肝臓がんに栄養を運んでいる肝動脈から抗がん薬を注入して治療します。
6-6.薬物療法
全身薬物療法で、以下のような治療薬を用います。
- 免疫チェックポイント阻害薬:免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬
- 分子標的薬:がん細胞に特異的な分子をめがけて攻撃する薬(注4
6-7.肝移植
健康な人から肝臓の一部を取り出し、臓器を受け取る人に移植する手術です。
6-8.緩和ケア
肝臓がんによる症状、治療に伴う副作用、後遺症などを軽くする治療です。 さまざまな症状への対策があります。
7.肝臓がんの余命
肝臓がんの余命は、病期、肝臓の機能などによって異なるため、一律には決められません。
代わりになる指標として5年生存率を示します。
5年生存率とは肝臓がんと診断されてから5年後に生きている確率です。 病期によって異なり、病期が進むほど生存率が下がります。
Ⅰ期:63.0%
Ⅱ期:45.2%
Ⅲ期:16.0%
Ⅳ期:4.4% (注7
まとめ
肝臓がんとは肝臓の細胞ががん化したものです。
原因は慢性肝炎・肝硬変などです。
慢性肝炎・肝硬変がみられる場合、食欲不振・むくみなどの症状がみられます。
肝臓がんは、腹部エコー・CT・MRIなどで診断します。
肝臓がんの数、大きさ、脈管への広がり、リンパ節転移、遠隔転移の有無により、ステージⅠ~Ⅳに分類されます。
治療としては、肝切除、焼灼療法、塞栓療法、肝動注化学療法などがあります。
肝臓がんの病期が進むほど5年生存率が下がります。
参考資料
注1)肝がんの病気について|国立がん研究センター
注2)肝癌診療ガイドライン2021年版|日本肝臓学会
注3)Gd-EOB-DTPAを用いた HCCのMRI診断 – PDF
注4)肝臓がん(肝細胞がん) 治療 - がん情報サービス
注5)肝癌治療:ラジオ波焼灼療法(RFA)|国立国際医療研究センター国府台病院
注6)生体肝移植|国立成育医療研究センター
注7)院内がん登録生存率集計結果閲覧システム - 肝細胞がん5年生存率