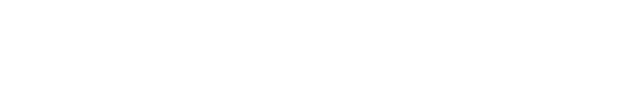胃潰瘍
胃潰瘍とは?
胃潰瘍とは、胃の内側を覆っている粘膜が深く傷つき、えぐれるように欠損した状態のことです。軽い炎症である「胃炎」とは異なり、胃酸によって粘膜が筋層にまで深く達するような損傷をきたすのが潰瘍の特徴です。
本来、胃の内側は強い酸(胃酸)から自身を守るための粘液や血流によって保護されています。しかし、何らかの原因でこの「防御機構」が機能しなくなると、胃酸が自分自身の粘膜を攻撃してしまい、潰瘍が生じます。
潰瘍は「胃炎」と異なり、粘膜の深層にまで達するため、出血や穿孔(胃に穴が開くこと)といった重大な合併症を引き起こすこともあります。
急性胃潰瘍と慢性胃潰瘍の違い
胃潰瘍には、その発症や経過のしかたによって「急性型」と「慢性型」に大別されます。
急性胃潰瘍は、突然発生し、比較的短期間で治癒することが多い潰瘍です。
手術や大きな外傷、重度のストレス、非ステロイド性抗炎症薬(ロキソニンなどの痛み止め)などが引き金になります。潰瘍は比較的浅く、周囲の粘膜は正常なこともありますが、出血しやすい傾向があります。
慢性胃潰瘍は、ピロリ菌感染や長期的な生活習慣の乱れ、非ステロイド抗炎症薬の長期継続使用などを背景に、長期間にわたって再発と治癒を繰り返すタイプの潰瘍です。周囲の粘膜が厚くなることや瘢痕(治った跡)がみられ、放置すると胃の変形や狭窄を起こすこともあります。
両者は発症のきっかけや経過が異なるため、診断後の治療や予防のアプローチにも違いが出てきます。
なぜ潰瘍になるのか?
私たちの胃は、強力な胃酸を分泌する一方で、自らを守るための粘液や血流といった防御機構を持ち合わせています。潰瘍は、この「攻撃」と「防御」のバランスが崩れることで発症します。
このバランスが崩れると、胃粘膜は胃酸の働きで組織や細胞分解され、深い潰瘍となるのです。
胃潰瘍はがんになるの?
基本的に胃潰瘍そのものが直接がんに進行することは稀です。
しかし、以下の点に注意が必要です:
- 潰瘍のように見える胃がんが存在する(「潰瘍型胃がん」)
- 繰り返す胃潰瘍の背景にピロリ菌感染があると、胃がんのリスクが高まる
- 高齢者では、がんと潰瘍の区別がつきにくいことがある
そのため、胃潰瘍が見つかった場合には、内視鏡検査と組織検査(生検)で「がんとの鑑別」が必須となります。
胃炎との違い
|
項目 |
胃炎 |
胃潰瘍 |
|
粘膜の傷の深さ |
表面的 |
深くえぐれている |
|
主な症状 |
軽度の胃もたれ、むかつき |
空腹時痛、みぞおちの強い痛み、出血 |
|
出血リスク |
少ない |
あり(吐血・黒色便) |
|
治療の必要性 |
状況による |
原則として治療が必要 |
胃炎は「炎症」の状態で、比較的軽度なことが多いですが、胃潰瘍はより重篤で、適切な診断と治療が必要です。
原因
胃潰瘍の原因は、大きく2つに分けられます。
-
ピロリ菌感染(Helicobacter pylori)
胃に住みつく細菌で、長期感染により胃の防御機能が低下します。日本人では中高年に多く、胃がんのリスクも上げるため、除菌治療が勧められます。
-
薬剤性(特に非ステロイド性抗炎症薬)
痛み止め(ロキソニンやイブプロフェンなど)の長期使用により、胃粘膜が傷つきやすくなります。特に高齢者ではリスクが高くなります。
-
ストレスと生活習慣
強いストレスや過労、睡眠不足などは、自律神経のバランスを崩し、胃酸の分泌や血流に影響を与えます。とくに重症疾患や手術などの身体的ストレスは、「ストレス潰瘍」と呼ばれる深刻な潰瘍を引き起こすことがあります。
-
喫煙と飲酒
喫煙は胃粘膜の血流を減らし、修復力を妨げます。アルコールは胃酸の分泌を促進し、粘膜を直接刺激する作用があります。とくに空腹時の飲酒は、潰瘍のリスクを一層高めます。 -
刺激物の摂取
唐辛子、胡椒、カフェイン(コーヒーや緑茶)、濃い味付けの食事などの刺激物も、胃酸の分泌を促進し、粘膜を刺激します。これらの摂取が直接潰瘍の原因となるわけではありませんが、既に粘膜が弱っている場合には症状を悪化させたり、再発の引き金になったりすることがあります。とくに空腹時の刺激物摂取は避けるべきです。
その他、遺伝的要因なども関与します。
症状
胃潰瘍の症状は次のようなものがあります。
- みぞおちの痛み(特に空腹時)
- 胃もたれ、吐き気
- 食欲低下
- 吐血(コーヒーかすのような嘔吐物)
- 黒色便(タール便)=出血のサイン
- 重症では胃穿孔による激しい腹痛や腹膜炎
ただし、高齢者では無症状のこともあり注意が必要です。
診断・検査方法
胃潰瘍の診断には以下の検査が使われます。
-
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
直接粘膜の状態を観察できる最も確実な方法です。必要に応じて組織を採取し、がんとの鑑別も行います。 -
ピロリ菌検査
尿素呼気試験、便中抗原、血中抗体、内視鏡での迅速ウレアーゼ試験(胃の組織pH検査)などで確認します。 -
血液検査・便潜血検査
出血の有無や貧血の程度を評価します。
治療方法
胃潰瘍の治療は、原因に応じて以下のように行います。
1.薬物療法
潰瘍の直接的な原因は、胃酸による粘膜の損傷です。そのため、まず行うべきは「胃酸を抑えること」です。
代表的な薬には以下の2種類があります。
*PPI(プロトンポンプ阻害薬):オメプラゾール、ランソプラゾールなど。
長年にわたり胃潰瘍治療の中心です。
*P-CAB(カリウムイオン競合型アシッドブロッカー):ボノプラザンなど。
PPIよりも即効性が高く、より強力に酸分泌を抑えます。
*粘膜保護薬:粘膜の再生を助ける補助的な薬です。
これらの薬は通常、数週間〜2か月程度の内服で潰瘍の治癒が期待できます。
2.ピロリ菌除菌
潰瘍の原因がピロリ菌感染である場合、除菌治療が必須です。
一般的な除菌法は、「胃酸抑制薬+2種類の抗生物質(アモキシシリンとクラリスロマイシン)」を1週間内服する三剤併用療法です。
除菌後には尿素呼気試験などで、確実に菌が消えたかを確認します。除菌に成功すれば、潰瘍の再発率は劇的に下がります。
3.薬の見直し
NSAIDsを使っていた場合は中止または胃粘膜保護薬を併用します。
4.出血がある場合
緊急内視鏡で止血処置を行うことがあります。
胃潰瘍を繰り返さないために ― 日常生活でできる5つの予防習慣
胃潰瘍は適切な治療で治る病気ですが、再発しやすい特徴があります。
特に、ピロリ菌感染の既往がある方や、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を継続使用する必要がある方では、日常生活の中で「守るべきポイント」を意識することが、症状の再燃や重症化を防ぐカギになります。
-
規則正しい食事と睡眠リズムを保つ
不規則な生活は自律神経を乱し、胃酸分泌のバランスにも影響します。
- 朝食を抜かず、1日3回、決まった時間に食事を摂る
- 空腹時間が長くなりすぎないようにする(胃酸が粘膜を攻撃しやすくなるため)
- 睡眠不足を避け、なるべく同じ時間に就寝・起床する
これらは胃の粘膜の修復力を高め、自然治癒力のサポートにもなります。
-
喫煙・過度な飲酒を避ける
喫煙は胃粘膜の血流を減少させ、修復力を著しく損ないます。また、アルコールは胃酸の分泌を促進し、粘膜を直接刺激します。
- 禁煙が最も望ましい
- 飲酒は週数回までにとどめ、空腹時の飲酒は避ける
- 強い蒸留酒やストレート酒は避け、飲むなら食後に少量
-
刺激物の摂りすぎに注意
香辛料・カフェイン・酸味の強い食品などは、胃粘膜を刺激することがあります。
- 唐辛子・こしょう・わさびなどの香辛料を大量に摂らない
- 空腹時のコーヒーや濃い緑茶を控える
- 酸味の強い柑橘類や酢の摂取もほどほどに
ただし、刺激物をすべて排除する必要はなく、個人差が大きいため、症状が出た時に振り返る姿勢が大切です。
-
ストレスマネジメントを心がける
慢性的なストレスは胃酸分泌を促し、粘膜の血流を低下させます。
- 睡眠時間を確保し、休日には意識的に休む
- 趣味や軽い運動でストレスを発散する
- 自分なりの「気分転換法」を見つけておく
精神的なストレスだけでなく、「忙しすぎて食事を抜く」「胃が痛いのに無理をする」といった身体的なストレスも避けるべきです。
-
自己判断で薬を中断しない
症状が改善したからといって、胃酸抑制薬を自己判断でやめてしまうと、潰瘍が再発しやすくなります。
- 医師の指示に従い、処方された期間はしっかり内服する
- NSAIDsやアスピリンなどを継続する場合は、胃薬(PPI/P-CAB)を併用して予防する
- 市販薬の服用も、かかりつけ医に相談を
胃を守るには「攻めすぎない」「無理をしない」日常が大切
胃潰瘍の予防は、何かを特別に始めるというよりも、自分の胃に過度な負担をかけない生活を心がけることに尽きます。症状がなくても、過去に潰瘍を経験した方やリスクが高い方は、ちょっとした生活習慣の改善が将来の再発防止につながります。
まとめ
胃潰瘍は、痛みなどの症状だけでなく、時に重大な合併症を引き起こす病気です。
しかし、適切な検査と治療を受ければ、しっかりと治すことができます。
「みぞおちの痛みが続く」「黒い便が出る」「胃薬を飲んでも良くならない」といった症状がある場合は、早めに当院を受診ください。