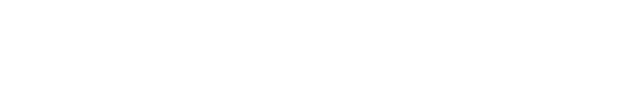高血圧
高血圧はなぜ治療が必要なの?理由と治療法を解説します
高血圧はよくある病気ですが、どうして治療が必要なのでしょうか?
その理由を知りたい方は多いはずです。
本記事では、高血圧の基準、原因、症状、合併症、治療について解説します。
これを読めば、高血圧のことがよく分かるでしょう。
血圧が気になる方は役立ててみてください。
1.高血圧の基準
血圧の値は、診察室で測った場合(診察室血圧値)と家庭で測った場合(家庭血圧値)で異なることがあり、それぞれの場合で高血圧の基準が決められています。
診察室と家庭で測った値が異なる場合は、家庭血圧値を優先させます。
つまり家庭血圧値だけでも高血圧の判定が可能です。
さらに血圧の高さによってⅠ~Ⅲ度の高血圧に分類します。
1-1.診察室血圧値
高血圧:140/90mmHg以上
| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | ||
| Ⅰ度高血圧 | 140~159 | かつ/または | 90~99 |
| Ⅱ度高血圧 | 160~179 | かつ/または | 100~109 |
| Ⅲ度高血圧 | ≧180 | かつ/または | ≧110 |
収縮期血圧と拡張期血圧で分類が異なる場合は、高い方の分類に組み入れます。
たとえば収縮期血圧がⅠ度、拡張期血圧がⅡ度の場合はⅡ度高血圧です。
1-2.家庭血圧値
高血圧:135/85mmHg以上
| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | ||
| Ⅰ度高血圧 | 135~144 | かつ/または | 85~89 |
| Ⅱ度高血圧 | 145~159 | かつ/または | 90~99 |
| Ⅲ度高血圧 | ≧160 | かつ/または |
収縮期血圧と拡張期血圧で分類が異なる場合は、高い方の分類に組み入れます。
2.高血圧の原因
高血圧の85~95%は原因が不明です。
原因不明の高血圧を原発性高血圧、特定の原因がある高血圧を二次性高血圧とよびます。
2-1.原発性高血圧
全高血圧の85~95%を占め、以前は本態性高血圧とよばれていました。
はっきりした原因は分かっていませんが、血圧の調節に関わる細動脈の収縮に遺伝性の異常が影響しているのではないかと推定されています。
2-2.二次性高血圧
特定の原因による高血圧であり、全高血圧の5~15%を占めます。
二次性高血圧の種類を示しますが、詳細は省略します。
- 腎実質性高血圧:慢性糸球体腎炎・多発性嚢胞(のうほう)腎など
- 腎血管性高血圧:腎動脈狭窄症など
- 内分泌性高血圧:原発性アルドステロン症・クッシング症候群・褐色細胞腫など
- 血管性高血圧:高安動脈炎・大動脈縮窄症など
- 脳・中枢神経系疾患による高血圧
- 遺伝性高血圧
- 薬剤誘発性高血圧:非ステロイド性抗炎症薬・カンゾウ・グリチルリチン・グルココルチコイドなどによるもの
3.高血圧の症状
大半の高血圧は特に何も症状がありません。
ただし重度の高血圧を長い間放置していると、まれに高血圧性脳症、高血圧緊急症を起こすことがあります。
3-1.初期症状
初期の高血圧では何も症状はみられません。
頭痛やめまいを高血圧の症状とみなす人がありますが、これは間違いです。
これらの症状は高血圧でない人にも同じようにみられます。
3-2.高血圧性脳症
重度の高血圧を長い間放置していると脳が腫れて、頭痛・吐き気・嘔吐・傾眠・けいれんなどがみられ、進行すると昏睡におちいることがあります。
これを高血圧性脳症とよびます。
3-3.高血圧緊急症
また重度の高血圧により心臓に負担がかかり、胸痛や息切れを起こすことがあります。
ときに大動脈が破裂して激しい胸痛や腹痛を起こします。
こういった状態は高血圧緊急症とよばれ、緊急の治療が必要です。
3-4.二次性高血圧
特定の原因となる病気がある高血圧では、その病気特有の症状が現れます。
詳細については省略します。
4.高血圧の合併症
重度の高血圧を長い間放置していると、全身に影響を及ぼして合併症を起こします。
高血圧の治療が必要な理由は、この合併症を防ぐためです。
4-1.脳血管障害
高血圧があると脳出血・クモ膜下出血・脳梗塞などの脳血管障害(脳卒中)を起こしやすくなります。
症状は突然に起こり、麻痺、体の片側の感覚障害、視力障害、発話困難、バランス障害などがみられ、出血の場合は激しい頭痛を起こすことがあります。
世界的に脳血管障害は2番目に多い死因であり注意が必要です。
高血圧以外に脂質異常症・糖尿病・喫煙・肥満・過度の飲酒・運動不足などが脳血管障害を起こすリスクを高めます。
4-2.心疾患
高血圧が長い間続いていると、心臓に負担がかかり、心臓の壁が厚くなって心臓が拡大します。
その結果心臓のポンプ機能がうまく働かなくなり、心不全を起こします。
また血管にも負担がかかって、動脈硬化が進み、血管の内腔が細くなったり、つまったりします。
その結果、狭心症・心筋梗塞といった虚血性心疾患を起こします。
4-3.腎疾患
動脈硬化のために腎臓を養う血管も損なわれ、腎臓への血流が低下します。
その結果、腎臓の機能が低下して慢性腎臓病や腎不全を起こします。
症状として、体のむくみ、かゆみ、疲労、吐き気などがみられ、寿命が縮みます。
4-4.血管疾患
動脈硬化および血管壁への圧力が原因で、大動脈解離、閉塞性動脈硬化症を起こすことがあります。
大動脈解離は、何の前触れもなく突然に大動脈が裂けて出血し、激しい胸痛あるいは腹痛を起こし、かなり高い確率で死にいたる恐ろしい病気です。
閉塞性動脈硬化症は、下肢の動脈の内腔が細くなり、やがてつまってしまい、下肢の血流が途絶えて壊死を起こす病気です。
下肢切断や死亡の原因になります。
5.高血圧の治療
高血圧治療の目標は、血圧を診察室血圧で130/80mmHg未満、家庭血圧で125/75mmHg未満に下げることです。
ただしこの血圧になると、めまい、ふらつきなどが現れる場合は、140/90mmHg未満などを目標にします。
治療法として食事療法、禁煙、飲酒量制限、運動療法、降圧薬があります。
5-1.食事療法・禁煙・飲酒量制限
日本人の塩分摂取量は外国と比較すると多い傾向があり、男性で10.8g/日、女性で9.1g/日と報告されています。
食塩の摂取量を減らすと血圧は低下するため、6g/日未満を目標にして減塩してください。
日本人のカリウム摂取量は、男性で2,382mg/日、女性で2,256mg/日と報告されています。
カリウムは体内のナトリウムの排せつを促すため、3,000mg/日摂取が望まれます。
野菜・果物などカリウムを多く含む食物を十分に取ってください。
肥満は高血圧の発症リスクであり、ダイエットで体重を減らすことが重要です。
体重を1.0kg減らすと収縮期血圧が約1.1mmHg、拡張期血圧が約0.9mmHg低下するとされています。
つまり肥満の人が体重を10kg減らせば血圧が10mmHgほど低下するわけです。
また糖尿病の人、コレステロール値が高い人は、飽和脂肪や総脂肪含有量の少ない食事が必要です。
さらに喫煙、過剰な飲酒は高血圧のリスクを高めるため、禁煙と飲酒量制限が必要です。
毎日の飲酒量は、男性で2ドリンク以内(ビール500mL、ワイン240mL、ウイスキー60mL以内)、女性で1ドリンク以内(ビール250mL、ワイン120mL、ウイスキー30mL以内)が適量です。
5-2.運動療法
有酸素運動は血圧を下げる効果があります。
有酸素運動を続けることで収縮期血圧が2~5mmHg、拡張期血圧が1~4mmHg低下することが期待されています。
有酸素運動は体重、体脂肪を減らす効果もあります。
また2型糖尿病の発症を抑え、脂質異常症を改善します。
ウォーキング・ジョギング・ランニング・サイクリングなどを1回30分以上、週に3日以上、できれば毎日続けてください。
ただし合併症のために運動を制限されている人は、主治医の指示に従うことが必要です。
5-3.降圧薬
食事療法・運動療法を3カ月ほど行っても十分に血圧コントロールができない場合、もしくはⅢ度高血圧などで速やかな降圧を必要とする場合は、高圧薬で治療します。
降圧薬にはさまざまな種類がありますが、Ca拮抗薬、ARB、ACE阻害薬、利尿薬、β遮断薬の5種類が主に用いられます。
持病や禁忌に応じて適切な降圧薬が選択されます。
降圧薬は1日に1回投与を原則としますが、24時間にわたり十分な降圧が必要です。
可能ならば1剤のみで治療し、コントロールが難しい場合は2~3剤を併用します。
2剤使う場合は、ARBまたはACE阻害薬+Ca拮抗薬、ARBまたはACE阻害薬+利尿薬、Ca拮抗薬+利尿薬の組み合わせがおすすめです。
6.まとめ
診察室血圧値が140/90mmHg以上、家庭血圧値が135/85mmHg以上の場合を高血圧とよびます。
高血圧の85~95%は原因が不明です。
そして大半の高血圧は特に何も症状がありません。
にもかかわらず治療が必要なのは、さまざまな合併症を引き起こすからです。
合併症として、脳血管障害、心疾患、腎疾患、血管疾患があります。
高血圧治療の目標は、血圧を診察室血圧で130/80mmHg未満、家庭血圧で125/75mmHg未満に下げることです。
治療法として食事療法、禁煙、飲酒量制限、運動療法、降圧薬があります。
参考資料
- 高血圧治療ガイドライン2019 PDF(8.7MB) – 日本高血圧学会
- 高血圧 - MSDマニュアル