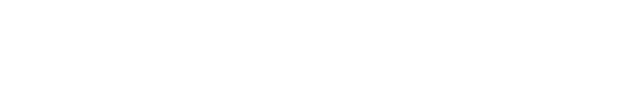胃がんとは?
病態・原因・検査・ステージ・治療について解説
胃がんは日本人に多くみられるがんです。
早期発見と治療が大切であり、胃がん検診は早期発見に有用とされています。
それでは胃がんとはどのような病気なのでしょうか?
この記事では、胃がんの疫学、病態、原因、症状、検診、検査、ステージ、治療について解説します。
これを読めば胃がんの概要が理解できます。
胃がん検診を受ける際に役立ててみてください。
胃がんとは
胃がんとは胃の壁の内側をおおう粘膜にできるがんです。
がんが大きくなるにつれて、胃粘膜の深部に広がります。
胃の壁を突き抜けると、胃に接している大腸、膵臓、横隔膜、肝臓に直接浸潤します。
おなかの中にがん細胞が散らばることもあり、これを腹膜播種(ふくまくはしゅ)と呼びます。
またリンパ液、血液を介して、胃から離れた臓器へ転移することもあります。(注1
胃がんの疫学
日本全国で調査された胃がんに関する疫学データを示します。
- 胃がんと診断された数(2019年):124,319例
- 死亡数(2020年):42,319人
- 5年相対生存率(胃がん以外の死亡例を除いて、5年後に生きている胃がんの人の割合):66.6% (注2
このように日本では、多くの胃がんがみられ、死亡者数も相当にあります。
胃がんの病態・原因
胃がんでみられる構造や機能の変化(病態)と、それを引き起こす原因について解説します。
病態
そもそも「がん」とは、体にできるがん細胞の塊です。
がん細胞は、遺伝子変異によって死ななくなった細胞です。
人の体は約60兆個の細胞からなり、毎日1%くらいの細胞が死んでいます。
そのため細胞分裂で細胞を補います。
細胞分裂の設計図は遺伝子であり、毎日遺伝子を数千億回コピーしながら細胞分裂をくりかえします。
そしてときにコピーミスが起こり細胞は突然変異します。
細胞が死ななくなり、止まることなく分裂を繰り返すようになったものが「がん細胞」です。
健康な人でも毎日がん細胞ができます。
ただし免疫細胞(リンパ球)ががん細胞を退治し、ほぼ全てのがん細胞は退治されます。
しかしときにがん細胞が生き残ることがあります。
そして10~20年かけて細胞分裂し、大きな塊となったものが「がん」です。(注3
原因
がんは老化の一種であり、長生きすることでがん細胞が増えます。
長生きすればするほど免疫細胞の働きが衰えて、がんを発生しやすくなります。(注3
また胃がんの発生には、ヘリコバクター・ピロリの感染、喫煙、高塩分食品の摂取が関係しています。(注1
胃がんの症状
胃がんの症状は病期によって異なります。
初期症状
初期の胃がんはほとんど症状がありません。
たいていの場合、初期の胃がんは検診時にみつかります。
また胃潰瘍などで内視鏡検査を受けた時にみつかることもあります。(注1
進行時の症状
胃がんは進行すると、胃の痛み、もたれ、胸やけ、吐き気、食欲不振、体重減少などの症状を起こします。
また胃がんが出血すると貧血となり、黒い便がみられます。
ただし胃潰瘍、胃炎でも同じ症状がみられるため、症状だけで胃がんとは分かりません。(注1
末期の症状
さらにがんが進行すると、体の栄養を奪い取ってしまうため、やせ衰えます。(るいそうと言います)
また周囲の臓器へ広がり悪影響を及ぼします。
脳や肺などに転移してさまざまな身体症状を起こすこともあります。(注3
胃がん検診
胃がん検診は、50歳以上で症状がない健康な人を対象にして定期的に行われます。(自治体によります)
胃がんを早期に発見し、適切に治療することにより、胃がんによる死亡を減少させるのが目的です。
問診、胃部レントゲン検査(バリウム検査)あるいは上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)が行われます。
検診結果が「要精密検査」になれば胃カメラで精密検査が必要です。(注1
1次検診で胃カメラ検査をして「要精密検査」となった場合、再度胃カメラ検査をする場合があります。その際は胃カメラ検査に加え色素撒布や胃粘膜生検がおこなわれます。
胃がんの検査
胃がんの検査には、上部消化管内視鏡検査・胃X線検査・CT検査・MRI検査・PET検査・注腸検査・大腸内視鏡検査・審査腹腔鏡が含まれます。(注1
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
口や鼻から内視鏡を挿入して胃の内部を直接観察する検査です。
胃がんが疑われる部分の広がり・深さを調べます。
組織をつまみ(生検)、顕微鏡で「がん」かどうか、がんならばどのような種類かを判断します。
また内視鏡を使って、胃の中で超音波検査をすることもあります。(注1
胃X線検査(バリウム)
バリウムと空気をのむことで、レントゲンに胃が映るようにして、胃の形、粘膜の形状を調べる方法です。
この検査は胃内視鏡と比べると、胃全体の形や胃がんの広がりが分かりやすいのが特徴です。(注1
例えて言うならば影絵のような仕組みで胃の内部のコントラストをつけて病変の有無を調べます。
CT検査・MRI検査
胃の周囲への胃がんの浸潤、離れた臓器への転移の有無を調べます。
この検査によって、後に記載する胃がんのステージが決まります。(注1
PET検査
放射性フッ素を含むブドウ糖を注射して、がん細胞に取り込まれるブドウ糖を検出する方法です。
CT・MRIで見つけにくいがんが分かります。(注1
注腸検査・大腸内視鏡検査
注腸検査は肛門からバリウム・空気を注入してX線写真を撮る方法です。
大腸内視鏡検査は肛門から内視鏡を挿入して大腸の内部を観察する方法です。
胃のそばにある大腸へ、がんが浸潤していないかを調べます。(注1
審査腹腔鏡
全身麻酔をかけて、おなかに小さな穴を開け、腹腔鏡を挿入し、おなかの中を観察する方法です。
がん細胞がおなかの中へ散らばっていないか(腹膜播種)を調べます。(注1
腫瘍マーカー
血液検査でCEAやCA-19-9といった腫瘍マーカーを調べます。
腫瘍マーカーとはがん細胞、がんに反応した細胞で作られるたんぱく質です。
手術後の再発の有無、化学療法の効果判定などに利用されます。
胃がんのステージ(進行度分類)
胃カメラ検査、CT、MRI、腹腔鏡などの検査結果から、以下のような胃がんの進行度を求めます。
- 胃がんの深さ(T)
- リンパ節転移の有無と範囲(N)
- 遠く離れた臓器への転移の有無(M)
| N0:領域リンパ節に転移がない | N(+):領域リンパ節に転移がある | |
|---|---|---|
| T1:がんが胃の粘膜、粘膜下層にとまる T2:がんが胃の筋層に及んでいる |
ステージⅠ | ステージⅡA |
| T3:がんが胃の筋層を超えて漿膜下層に届く T4a:がんが胃の表面に出ているが他の臓器には及んでいない |
ステージⅡB | ステージⅢ |
| T4b:がんが他の臓器に及んでいる | ステージⅣA | |
| M1:肺や肝臓に転移している | ステージⅣB | |
(注4
胃がんの治療
ステージによって治療法を決めます。
早期胃がんについては内視鏡治療を先行して治療します。肉眼的・組織学的に進行胃がんと診断された場合は外科手術が主な治療法です。
- 深達度が粘膜層まで(T1a)でN0のもの:内視鏡切除を考慮
- 深達度が粘膜下層まで(T1b)でN0のもの:胃切除+胃のすぐそばのリンパ節を郭清
- 深達度が粘膜下層まで(T1)でN(+)のもの:胃切除+胃から少し離れたリンパ節も郭清
- T2, T3, T4で、大きなかたまりを作ったリンパ節転移のない場合:胃切除+胃から少し離れたリンパ節も郭清
- T2, T3, T4で、大きなかたまりを作ったリンパ節転移がある場合:術前化学療法+拡大手術を考慮
- M1:化学療法、放射線療法、緩和手術、対処療法、転移の状況によっては術前化学療法+拡大手術が行われることもある
さらに手術後にステージに応じて補助化学療法を追加します。
- ステージⅠ:補助化学療法なしで経過観察
- ステージⅡ、Ⅲ(T1およびT3・N0を除く):補助化学療法追加 (注5
まとめ
胃がんとは胃の壁の内側をおおう粘膜にできるがんです。
2019年には全国で124,319例の胃がんがみられました。
早期発見が重要ですが、初期には症状がほとんど全くみられません。
そのため胃カメラ検査または胃レントゲン検査を使った胃がん検診を受けることが重要です。
胃がんが疑われる場合は胃カメラ検査で診断して、CT検査・MRI検査・PET検査・注腸検査・大腸内視鏡検査・審査腹腔鏡などで胃がんのステージを決めます。
ステージに合わせて、内視鏡治療・手術療法・化学療法・放射線療法などで治療します。
早期発見して適切に治療すれば、胃がんは根治が見込める疾患です。