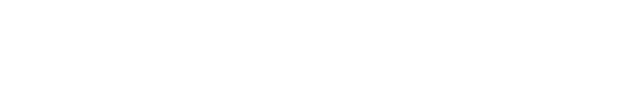睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?
睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、眠っている間に呼吸が何度も止まる病気です。
医学的には、10秒以上の呼吸停止が繰り返し起こる状態を指します。この呼吸の中断により睡眠の質が著しく低下し、日中の強い眠気や集中力の低下など、日常生活にさまざまな影響を及ぼします。また、十分な酸素が取り込めないことで、全身の健康に悪影響を及ぼすこともあるため、軽視すべきではない病気です。
主な症状(睡眠時・起床時・日中)
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状は、睡眠中だけでなく、起床直後や日中にもさまざまな形で現れます。以下のように分類して把握することで、早期発見につながります。
【睡眠中の症状】
- 大きないびき(断続的、むせるようないびき)
- 呼吸が止まる(家族から指摘されることが多い)
- 窒息感や息苦しさで目が覚める
- 頻繁な寝返りや寝汗
- 夜間の頻尿(睡眠が浅くなっているサイン)
【起床時の症状】
- 頭痛(特に前頭部)
- のどの渇きや違和感(口呼吸の影響)
- 熟睡感がなく、疲れが残っている
- 寝起きが悪く、スッキリしない
【日中の症状】
- 強い眠気(会議中、食後、運転中などでも眠くなる)
- だるさ・倦怠感
- 集中力の低下、物忘れ
- イライラや気分の落ち込み
- 性欲の低下や抑うつ傾向
これらの症状が複数当てはまる場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。本人に自覚がなくても、周囲の人の観察や助言が診断のきっかけになることも多いため、家族やパートナーからの「いびきがひどい」「息が止まっていた」という指摘は重要なサインです。
原因
SASは大きく2つのタイプに分類されます。
-
閉塞型(OSA)
最も多く見られるタイプで、睡眠中に喉の筋肉がゆるむことで気道がふさがれ、呼吸が妨げられる状態です。肥満や扁桃肥大、首周りの脂肪が多いこと、あごの形状などが主な原因となります。
-
中枢型(CSA)
脳の呼吸中枢がうまく働かず、呼吸の指令そのものが出なくなるタイプです。心不全や脳血管障害と関連することがあります。
また、アルコールや睡眠薬の使用も気道の筋肉を弛緩させ、SASを悪化させる要因になります。
診断・検査方法
SASが疑われる場合、次のような検査が行われます。
- 簡易検査:自宅でできる検査で、呼吸の状態や酸素濃度を測定します。検査機器を使って1〜2泊分のデータを記録します。
- 終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG):専門施設で一晩かけて脳波や筋電図、呼吸状態などを詳しく調べる精密検査です。確定診断に用いられます。
- エプワース眠気尺度:これは、日常生活の中で眠気をどの程度感じるかを数値化する問診票です。
【エプワース眠気尺度(ESS)質問票】
以下の8つの状況について、その場面でどれくらい眠くなるか・居眠りしそうになるかを、次のスケールにしたがって点数をつけてください。
<点数の基準>
- 0点:まったく居眠りしない
- 1点:まれに居眠りする
- 2点:ときどき居眠りする
- 3点:しばしば居眠りする
あなたが以下の状況に置かれた場合、どれくらい眠くなると思いますか?
|
状況 |
点数(0〜3) |
|
1. 座って読書しているとき |
|
|
2. テレビを見ているとき |
|
|
3. 公共の場(会議、劇場など)で静かに座っているとき |
|
|
4. 乗客として1時間以上、車に乗っているとき |
|
|
5. 午後に横になって休んでいるとき |
|
|
6. 座って誰かと話しているとき |
|
|
7. 昼食後(酒なし)静かに座っているとき |
|
|
8. 車を運転中、渋滞や信号待ちで数分間止まっているとき |
|
■ 合計点(0〜24点):_____
<判定の目安>
- 0〜10点:正常範囲(過度な眠気はない)
- 11〜14点:軽度の過眠(注意が必要)
- 15点以上:中等度~重度の過眠(医師への相談を強く推奨)
この質問票は、ご自身の睡眠の質や日中の眠気を把握するのに役立ちます。
SASの確定診断にはより詳細な検査(夜間ポリソムノグラフィー(PSG))が必要です。合計点が11点以上の場合は、睡眠時無呼吸症候群やその他の睡眠障害の可能性があるため、当院にてご相談ください。
治療方法
SASの治療には以下のような方法があります。
- CPAP(シーパップ)療法:鼻に装着したマスクから空気を送り込んで気道の閉塞を防ぐ方法で、最も効果的な治療法です。中〜重症の方に適応されます。
- 生活習慣の改善:体重管理、アルコール制限、禁煙、睡眠環境や睡眠姿勢の見直しなどが基本となります。
SASは治療によって症状の改善が見込める疾患であるため、適切な治療を早期に始めることが重要です。
合併症
SASは睡眠の問題だけでなく、以下のような全身の合併症を引き起こすリスクがあります:
- 高血圧
- 心臓病(心不全、狭心症、不整脈など)
- 脳卒中
- 糖尿病
- うつ病や認知機能の低下
夜間に繰り返される低酸素状態が、心臓や血管、代謝系に深刻な影響を与えるため、放置は非常に危険です。
日常生活でできる予防や改善方法
睡眠時無呼吸症候群を予防・改善するには、以下の生活習慣が効果的です。
- 体重を減らす:肥満が最大のリスク因子です。5〜10%の減量でも効果が期待できます。
- 飲酒を控える:特に就寝前のアルコールは気道の筋肉をゆるめ、無呼吸を悪化させます。
- 禁煙:上気道の炎症を引き起こし、気道を狭めるので禁煙は予防に有効です。
- 仰向け寝を避ける:横向きで寝ることで、気道の閉塞を防ぎやすくなります。
- 十分な睡眠時間を確保し、規則正しい生活を心がける
また、職場で定期的な健康診断を受けることも重要です。特に運転業務に従事している方は、定期的にSASの検査を受けることが勧められます。
まとめ
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、「ただのいびき」「疲れているだけ」と見過ごされがちですが、放置すれば日常生活や健康に深刻な影響を及ぼす病気です。日中の強い眠気や集中力の低下、家族からの「いびきがひどい」「息が止まっている」という指摘がある場合は、決して軽く考えず、早めに医師に相談しましょう。
現在は、簡易な検査や効果的な治療法も確立されており、早期に対応すれば、症状の改善や合併症の予防が十分に可能です。「質のよい睡眠」は、健康で安全な生活を送るための土台です。心当たりがある方はお気軽に当院にてご相談ください。